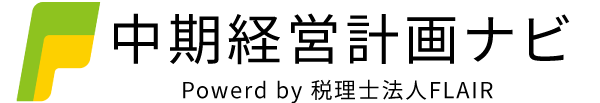経営とは終わりのない旅のようなものです。しかし目的地も定めず、地図も持たないままでは、旅というよりはただの放浪にすぎません。旅を安全で有意義なものにするには、きちんと目的地を定め、地図を準備し、下調べし、計画をたてることがかかせません。
旅であれば放浪も一興ではありますが、経営はそうは行きません。
会社経営は様々な人の支えがあって成り立つものです。しかし、どこへどのように向かっているのかが分からず放浪し、不測の事態に右往左往する会社を、従業員や取引先、そして金融機関が信用してくれるでしょうか。そもそも放浪する会社を経営者自身は果たしてうまく舵取りできるのでしょうか。
会社が成長し永続するためには、計画的で効率的に経営をすることが欠かせないことは想像に難くないでしょう。旅は後戻りできますが、経営に後戻りはないのです。
この記事では、中期経営計画の意義やメリット、策定のステップやポイントについて紹介します。
1.中期経営計画とは
経営は行き当たりばったりで上手くいくものではありません。そもそも「経営」という言葉は「事業目的を達成するために、継続的・計画的に意思決定をおこなって実行に移し、事業を管理遂行すること(小学館デジタル大辞泉)」とあります。
つまり事業目的の設定、計画の立案、管理の実行が前提となっているのです。経営をその言葉どおりに実行するために必要となるのが中期経営計画なのです。
中期経営計画は、経営理念やビジョン、経営者が持つ将来的な会社の経営についての考え、そして将来あるべき姿を、具体的かつ明確に示し、その「将来あるべき姿」と現状とのギャップを埋めていくために実行すべきことを3年から5年程度の期間でまとめた具体的な計画のことです。そして、その経営計画を書面にまとめたものを経営計画書と言います。
事業を永続させるためには、経営資源が限られるなかで売上や利益を安定的に上げ続けることが必要です。目先のことだけにとらわれていると、環境変化の予兆に気付けなかったり、想定外のことが発生した際に対応しきれず、売上や利益を確保できなくなる恐れがあります。
しかし中期経営計画を策定し、計画に基づいて行動することで、限られた経営資源を有効活用することができ、また計画の進捗を日々確認することで、変化の予兆にいち早く気づくことができるのです。
2.中期経営計画のメリット
(1)会社の現状や課題を整理することができる
事業を行っていると日々様々な課題に直面し、その対処に追われがちとなり、なかなか会社のことをゆっくり考える機会を設けることができません。緊急性はないものの重要な課題も先送りしがちとなります。
しかし中期経営計画を策定するとなれば、必然的に経営をゆっくり考え、自社の現状や課題を整理する時間をとらざるを得なくなります。それにより、組織の内部環境に関する情報を整理でき、市場の状況や、市場に占める自社や競合他社のシェアの割合などの外部環境も数字で把握する良い機会を設けることができるのです。
自社の状況を客観的に把握することができれば、自社が取り組むべき課題が明確になります。課題が明確になってこそ、自社がやるべきことを具体的に検討することができるのです。
(2)やるべきことが明確になる
経営計画がないまま経営を行うことは、目的地も曖昧なまま地図も持たずに放浪するのと大きな違いはありません。明確な目的地とそこまでの道筋を示す地図があるからこそ、突然の通行止めにあっても、迂回路を経由するなどして目的地に近づくことができるのです。漠然とした地名よりも具体的な歴史的建造物などを目指すほうが意義のある旅になるでしょう。
「売上や利益を何パーセントアップ」といった漠然とした目標ではなく、「5年後にこの事業分野で売上と利益をいくら達成する」など目標を明確に定めることで、具体的な計画を立てやすくなり、現場への落とし込みがスムーズになります。
具体的なアクションプランが立てられれば、会社あるいは部門、さらには従業員の一人一人まで、その日にやるべきことが明確になるのです。
(3)従業員のモチベーションが高まり、組織がまとまる
ほとんどの経営者は自社をどのような会社にしたいか、事業活動を通じて何を実現したいか、ビジョンやミッションを胸に抱いています。従業員もまた、お金のためにばかり働いているわけではなく、承認欲求や貢献欲求をもっています。このような経営者の理想像と従業員の貢献意識が共鳴することは決して少ないことではありません。
しかし、会社のビジョンやミッションが従業員に共有されていなければ、十分なパフォーマンスが発揮できないどころか、組織がまとまらずバラバラになってしまう可能性もあります。中期経営計画を作り、経営計画書などとして従業員と共有することで、そうしたビジョンやミッションを従業員全員に浸透させることができます。
会社のミッションやビジョンを従業員が理解することで、承認欲求や貢献欲求が刺激されてモチベーションが高まり、また具体的な目標や行動計画が明確に示されることで、そのモチベーションがパフォーマンスとして発揮されやすくなります。会社の方針を共有することで従業員のモチベーションを高めることができ、全員が同じ未来を目指して一丸となり、統率のとれた組織運営が可能となるのです。
(4) 社外からの信頼と関係性の強化
ビジネスパートナーを選ぶとしたら、明確な計画をもった相手とそうでない相手がいれば、誰しも前者を選ぶでしょう。いくら優れたビジネスモデルを有していても、計画性がなく成り行きで経営している会社に対しては、どうしても厳しい目で評価されてしまいます。事業を円滑に推進するためには、取引先や金融機関などの信用を高めなければなりません。
金融機関は融資判断にあたって、その会社の財務状況や担保力など定量評価を基本としながらも、その会社の事業の内容や成長可能性など定性評価も重視されています。金融庁が掲げる、いわゆる「事業性評価」です。
新規取引先は取引開始にあたって、帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査データを入手できますが、そこから得られる情報は限られています。
しっかりとした経営計画があることで、金融機関からの信用は大きくなり、スムーズに資金調達を進めることができるようになります。また取引先からの信頼を得ることができ、既存取引先との取引拡大や、新規取引先の開拓、仕入先や外注先との関係強化など、多くの恩恵を受けることができます。
中期経営計画を策定し、外部に発信することで、企業に対する社外からの信頼が高まり、事業活動が円滑になるのです。
(5)会社を存続し、成長させる
「ゴーイングコンサーン」という言葉があるように、会社は将来にわたり存続し続け、事業を継続していくことが求められています。
経営者自身はもちろんのこと、そこで働く従業員やその家族、そして顧客や取引先に対する責任として、会社を存続させ成長させていく社会的責任があるのです。しかし経営を取り巻く環境の変化は激しく、ときに想像を超える事象が発生するため、会社を安定的に成長させ存続させることは困難を伴います。
経営計画を作成することで、長期的目線で経営目標や経営戦略を考えることができますので、将来に起こりうる経営環境の変化を予測し、ビジネスチャンスをいち早く取り込むことが可能となります。
また計画と実績のギャップを認識することで、経営環境の変化をいち早く察知し反応することができ、不意に訪れる危機を回避することもできます。環境の変化に対応しながら企業を存続させ、成長させるために、経営計画はなくてはならないものなのです。
中小企業庁が公開している「2016年版 小規模企業白書」では、経営計画を作ることが売上増加に効果があることを示唆するデータがあるように、なりゆき任せの経営と比較し、計画的な経営のほうが成果が出やすいということは理にかなっています。
3.中期経営計画策定のステップ
(1)経営理念を定める
中期経営計画を策定するにあたって最初に行うことは、経営理念を定めることです。経営理念とは、会社の目的や存在意義、あるいは経営者の価値観や想いを表すもので、次の3つの要素から成り立っています。
①ミッション・・・会社の存在する目的、果たすべき使命、存在意義
②ビジョン・・・目指すべき将来の理想像、なりたい姿
③バリュー・・・会社が大切にする価値観、行動指針
会社は、自身の存在意義・使命(ミッション)を果たすことで、理想像・なりたい姿(ビジョン)の実現を目指すために、価値観・行動指針(バリュー)に基づいて、日々の事業活動を行うのです。
経営理念は経営の羅針盤であり、経営計画の大黒柱です。理念の無い計画は「画竜点睛を欠く」ことになりますので、まず最初に明確に定める必要があるのです。
(2)経営環境分析
経営理念を現実的な計画に落とし込むためには、経営環境を分析し、自社(内部環境)と市場や競合など(外部環境)をしっかり把握する必要があります。
内部環境の分析では、自社の現状を多面的に分析し、強み・弱みなどを整理します。過去3~5期の決算書データ、組織体系や人的資源、組織風土、自社商品の商品力など、同業他社と比較した客観的な分析を行います。
外部環境の分析では、自社を取り巻く環境を分析し、自社にとっての機会や脅威になりうつ要素を整理します。市場動向、社会情勢、顧客ニーズ、競合他社の状況など、現状だけでなく今後の動静を含め、中長期的視野で分析します。
内部環境と外部環境の分析を行うことで、会社の戦略や長期事業構想についてのアイデアが見えてきます。
(3)経営戦略立案
経営理念を明確化し、自社を取り巻く環境について分析した後は、経営戦略を立てます。
まずは、経営環境分析の結果をふまえた上で、経営理念の実現に向け、今後どの分野で事業を展開するのか、どの事業に注力していくか、事業領域=ビジネスドメインを決めていきます。
次に決定した事業領域における自社の位置付け=ポジションをふまえ、そのポジションにおける最適な施策を検討します。
最後に、その施策を実行するにあたって、どのように経営資源を投入するかを決定します。
以上のプロセスによって、経営戦略が定まります。
(4)目標の設定
経営戦略が決まったら、具体的な目標を定めます。戦略を具体的な行動計画まで落とし込み、また計画の進捗状況を測定・管理するために、数値的な目標を設定することが必要となります。
数値目標は売上目標や利益目標だけでなく、店舗数や従業員数、市場シェアなど具体的な目標を定めます。さらには利益率や生産性などの経営指標も設定します。目標は3~5年先を設定をしたうえで、1年単位の目標にまで分解します。
目標設定において重要なポイントは、合理性と実現可能性があり、社内外の納得感が得られるものとすることです。合理性、実現可能性が乏しいと思えるときは、経営戦略の見直しに立ち戻る必要があります。
(5)共有し、実行し、進捗状況を確認する
中期経営計画を作成して満足してしまう例は非常に多いです。せっかく作成した経営計画書も社長のキャビネットにしまい込んでしまっては何の意味もありません。中期経営計画は経営計画書にまとめて配布したり、経営計画発表会を開催するなど、社内で共有しましょう。
経営理念から経営目標まで、従業員の一人一人までしっかり浸透させることが重要です。特に各部門のリーダーやマネージャーは、現場レベルの目標や行動計画に落とし込めるまで、中期経営計画を正しく理解してもらう必要があります。
次に、中期経営計画を実行し、進捗確認を行います。各部門あるいは個々人が、中期経営計画を基に立案された日々の行動計画を実行に移し、月次単位などで計画と実績の差異を把握し、改善策を検討・実行していきます。着実な進捗管理のためには、会議体の設計などルールや仕組みづくりが重要になります。
4.中期経営計画策定の注意点・ポイント
中期経営計画の作成に躊躇する方の多くは、経営計画を作成方法がわからない、作成する時間がとれない、作成するメリットに懐疑的などの理由があるかと思います。そんな皆さんの精神的障壁を少しでも和らげるために、中期経営計画を作成する際のポイントをご紹介いたします。
(1)量より質を重視する
経営計画に限った話ではありませんが、どんなプランでもボリュームがあれば良いというわけではありません。
実のあるプランであれば簡素なものでも十分有効なものになります。最初から全ての要素を盛り込んだ完璧なプランに仕上げる必要はなく、最低限必要な要素だけをきちんと押さえていれば、有効な経営計画として十分機能します。
細かい不足があっても他のツールやコミュニケーションで補完はできます。特に初めて中期経営計画を作成しようとするときは、量より質を重視するよう心掛けましょう。
(2)テンプレートを活用する
中期経営計画は、策定ステップのセクションでご紹介したように、一定の型があります。ゼロから自力で経営計画を作成すると、多大な労力を要するばかりか、必要な要素が抜け落ちてしまいかねません。
その結果、途中で挫折したり、中途半端な内容になったり、失敗に陥る恐れがあります。そうならないよう、他社の経営計画を参考にしたり、テンプレートを活用することをお勧めします。
まずは他社事例やテンプレートは、経営計画に必要な要素がある程度網羅されていますので、これらを参考にしながら、自社に必要な要素を取捨選択し、作成をすすめて行けば良いのです。
中期経営計画はある一期だけ作成して終わりではなく、毎期修正しながら作成するものです。期を追うごとに自社オリジナルの経営計画のカタチが出来上がっていくのです。
(3)具体的な記載かどうかチェックする
経営計画のメリットの一つとして「やるべきことが明確になる」という点をあげました。しかし経営計画の記載内容が抽象的だと、何を目指してどう行動するかが分かりにくく、やるべきことが依然として不明確なままとなってしまいます。
経営計画は誰が読んでも理解がしやすく、課題と対策も明確になっており、具体的な行動がイメージしやすく、判断に迷わないよう、具体的な記載内容になっていることが重要なのです。
経営計画は現場レベルの行動計画まで落とし込んでこそ意味があります。中期経営計画で掲げる目標や戦略の内容が具体的であれば、現場レベルのタスクと期限の設定が容易になり、一人一人の社員の行動が変わるのです。
(4)PDCAサイクルを確立し、進捗管理を怠らない
中期経営計画を策定し、単年度計画や月次計画まで具体化し、具体的な行動計画まで立案しても、それを実践しなければ何の意味もありません。しかし計画を作成しっぱなしで計画倒れになっている例は非常に多いです。経営計画の策定はゴールではなく、スタートなのです。
計画を策定したら、定期的に進捗を管理する機会を設ける必要があります。会社を取り巻く環境は日々大きく変化していますので、四半期や半期ごとではなく、毎月のチェックが理想的です。
月次の目標と実績の差異、その原因の検討と次月に向けた改善のサイクルを継続していくのです。そのためには、毎月の実績を測定するツールや会議などの仕組みを構築することが欠かせません。
5.中期経営計画が必要な場面とは
(1)金融機関からの融資を受けたいとき
会社経営において資金繰りは生命線です。どんなに優れたビジネスモデル、どんなに優れた商品力があっても資金が枯渇すれば会社経営は行き詰まりますし、逆もまたしかりです。
会社の資金繰りを安定させるために、金融機関に融資を申し込むべき局面も出てくるでしょう。金融機関の融資を受けるためには、金融機関の審査を受けなければなりません。金融機関は融資判断にあたって、財務状況や担保力などの定量評価に加え、その会社の事業の内容や成長可能性など定性評価も重視します。
融資の申し込みにあたって、実現可能性が高く堅実な経営計画と返済計画を示すことができれば、スムーズに審査が進み、また計画に適した有利な融資枠組みを紹介してくれることもあります。
経営計画がないと、金融機関からの融資が受けられず、重大な機会損失を被り、最悪の場合は会社経営に行き詰ることにもなりかねません。会社の生命線である資金繰りを安定させるためにも、中期経営計画を作ったほうが良いと言えます。
(2)採用活動を行うとき
経営計画がないと、会社のビジョンに共感できる優秀な人材を集めることもできません。指標とするものが労働条件しかないから他社と比べてよい条件を提示できなければ、人材を集めることができなくなります。経営計画がなければ人材を集めることができず、長期的に会社を成長させることは困難になります。
採用活動において、しっかりした経営計画を示すことができれば、自社の経営理念に共感してくれる優秀な人材を集めることが可能になるでしょう。採用のミスマッチを避けることで、労使トラブルに発展するリスクも低減できるでしょう。
(3)新規事業を立ち上げるとき
会社の継続的な成長のためには、新しい商品やサービスの開発が必要です。ときには新しい事業展開や大幅な組織変更など、大きな変革が必要な場面も出てきます。
このような新たな取り組みをするにあたっては、具体的な計画の有無が成否を分けることになります。新規事業の立ち上げの失敗が会社の存亡を揺るがすような事態は避けなければなりません。
新規事業を成功させるためには、市場動向の調査と分析、具体的な事業計画や投資計画、そして資金繰り計画を綿密にたてることが必要です。また市場環境の変化を織り込んだ複数のシミュレーションと施策の検討、そして計画の修正など、柔軟な対応が鍵になります。
中期経営計画はこれらの要素が盛り込まれていますから、新規事業の成功可能性が高まることになるのです。
(4)助成金・補助金・その他の支援制度を活用したいとき
国や地方公共団体は、企業の成長を支援し経済を活性化させるための様々な補助金や助成金制度を提供しています。会社の安定や成長のためには、このような公的な支援制度の積極的な活用が有効です。
ただし、このような各種支援制度の申請にあたっては、事業計画の作成が必要となる場合が多く、申請準備期間も限られています。そのために、日頃から会社の経営計画を備えておくことが重要になるのです。
また国が定める様式に沿って経営計画を作成することで、国の支援や優遇を受けられるものもあります。代表的なものとしては、経営力向上計画、経営革新計画、先端設備導入計画などがありますので、これらの活用も中期経営計画があれば、自社の今後の取り組みが明確になっているため、公的支援制度の計画的な活用が可能となり、また申請準備も円滑に進めることができます。
(5)経営状況を改善したいとき
会社経営は常に順調に進むとは限りません。市場環境の急激な変化や、想定外の危機によって会社の存亡を揺るがすこともあるでしょう。このようなときは、会社の生き残りをかけ、すぐにでも何らかの対策を講じなければなりません。まずは現状を正確に把握し、今後の予測をたて、会社の課題と対策を明確に見定めることが必要です。
このようなときに中期経営計画があると、今後の損益や資金繰りなど、危機がもたらす自社への影響度を高い精度で予測することができます。
また、想定外の危機が現在の事業の前提条件を覆すようなこともあるでしょう。中期経営計画で定めた経営戦略があれば、現況と照らし合わせて、戦略見直しの方向性も検討がしやすくなります。
中期経営計画があれば、緩やかな市場環境の変化はもとより、急激な危機やトラブルへの対応にも有効に働くのです。
(6)事業承継を行うとき
「ゴーイングコンサーン」という言葉があるように、会社は将来にわたり存続し続けることが求められており、そのためには経営者の交代が必要となる局面があります。親から子への代替わりだけでなく、親族外の役員やM&Aによる第三者への承継など、事業承継の形態はさまざまですが、どのような形態であっても、円滑な事業承継を行うために中期経営計画の策定は欠かせません。
経営体制の変更は、社内の従業員や社外の利害関係者にとって、大きな関心事です。経営体制の変更が、安全、安心かつポジティブであることを明確に示すことが必要となります。これまでどおり、あるいはこれまで以上の理解と協力を仰ぐためにも、中期経営計画を活用して、新経営体制の今後のビジョンや方針を明確に示しましょう。
6.まとめ
この記事では、中期経営計画の意義やメリット、策定のステップやポイントについて紹介しました。
変化の激しい現代において、場当たり的な経営では、会社の成長どころか存続させることも難しいのが現実です。しかし中期経営計画があることで、具体的な目標設定や経営戦略に従って行動することができ、また変化にも柔軟に対応できるのです。会社の存続と成長のために、中期経営計画は欠かせないのです。
中期経営計画は全ての会社が作成するべき最重要の経営ツールです。経営計画書を作っていない会社は、ぜひこの機会にチャレンジし、会社の成長を目指しましょう!